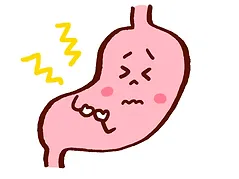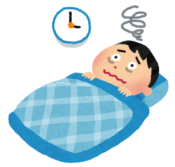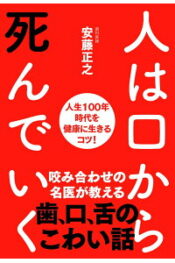胃薬が手放せない方必見
1つめは、とくに 水分の摂り過ぎによる胃腸疾患です。
現代人は、コンビニエンスストアの普及などで手軽に入手できるため、夏でも冬でも冷たい飲み物を摂る機会が多くなっています。
冷たい飲食物を多く摂ると体が冷やされ、体内の水分量は多くなります。
漢方では「胃を冷やすことは消化機能を低下させる大きな原因になる」と考えます。
胃が冷えてしまうと、胃のもたれや下痢、といったさまざまな症状を引き起こします。
2つめは、炎症性の胃腸症状です。
胃の炎症の多くの原因はピロリ菌です。
日本人の多くが感染しているといわれるピロリ菌ですが、そのままにしておくと、胃の不快な症状だけでなく、胃粘膜に炎症を起こし、萎縮性胃炎に進行してしまいます。

また、ストレスは胃腸に大きな影響を与えます。精神不安があったり、強いストレスを受けたりすると、胃やみぞおちの周辺が緊張して硬くなり、つかえを感じるようになります。そうなると、胸やけ、げっぷ、みぞおちが熱く感じる、といった炎症性の胃腸症状を起こしやすくなるのです。
ストレスが何故、胃腸に影響するのかを少しお話します。
様々なストレスにより自律神経が乱れてしまうと胃腸の働きに不調が起こります。
東洋医学では、自律神経に関わる肝(かん)の乱れが影響すると考えます。
自律神経は、自分の意思とは関係なく、呼吸、心拍、循環、消化などの機能をコントロールする神経です。
自律神経には、活動の神経である「交感神経」とリラックスの神経である「副交感神経」があります。この2つの神経がシーソーのようにバランスを取りながら働いています。 日常生活の中で自律神経がどちらかに傾いてしまうと、自律神経のバランスが乱れ、その影響がからだのあらゆる機能に及びます。
胃腸に関していうと、消化や吸収、排泄などが正常に機能しなくなり、胃腸の不調に繋がってしまいます。
●交感神経が優位になり過ぎると、胃の働きが鈍くなり、消化力が低下し胃もたれが起きます。
●副交感神経が優位になり過ぎると、胃酸の分泌が過剰になり、胃粘膜を荒らしてしまいます。
3つめは、胃腸虚弱タイプの方の胃腸疾患です。
ふだんから胃腸が弱い方は、胃腸のトラブルだけでなく、疲れやすい、かぜをひきやすいといったお悩みを併せもっていることが多いようです。
いわゆる脾虚(ひきょ)イプと言えます。
脾胃(ひい)とは、胃腸あるいは、消化器系全般の機能のことを言います。
そして虚している(エネルギー、パワー不足)ことを脾虚といいます。
体力がなく、食欲不振で、胃もたれ、胃内停水(おなかがチャポチャポする)などが起こりやすいです。
漢方や漢方系食品は胃のトラブルの改善が得意です。
胃のトラブル改善にヘルシーBOX立石薬店のオススメは、AHSSクロモリジン-G、マスマリン、醗酵紅参、安中散(あんちゅうさん)六君子湯(りっくんしとう)平胃散(へいいさん)があります。
AHSSクロモリジンやマスマリンには、抗ピロリ菌作用があります。
症状や原因による使い分けはお問い合わせください。